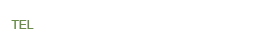国会の中で障害当事者が活躍する効果
は、速いっ! なんというスピードなんだ! 先日行われた参議院議員選挙にて、 山本太郎が旗揚げした“れいわ新選組”から出馬した重度障害のある2名の候補者が当選したことは歴史的快挙で、 今後の障害者施策が当事者目線で大きく変わっていくターニングポイントとなるのはおそらく間違いない。 いや、そうなるだろうと確信しています。 当選したのはALS(筋萎縮性側索硬化症)の舩後靖彦氏と脳性麻痺の木村英子氏。 お二人とも24時間介助なしでは自立した生活ができない重度障害者です。 しかし、しっかりとしたビジョンを持っていて、 重度障害があっても人として当たり前に生きていける地域社会を目指して、 それこそ命がけで闘ってこられました。 重度障害者が安心して暮らせる社会はすべての人にとって暮らしやすい社会になるだろうし、
今の社会から“バリア”がなくなって“フリー”となれば誰もが安心して生きられる社会になるはず。
そんな社会にしていくためにはまず国会から変えていく必要があります。
障害者が国会議員になった事例は過去にもあって、
少なからずバリアフリー化されてきた部分もありますが、
今回はスロープの設置とか本会議場の議席(スペース)の確保といった建物の物理的なバリアフリーだけでなく、
起立採決や記名投票といった障害故に不可能な表決方法の改善も必要で、
「仕事中はヘルパーを使えない」
という障害者総合支援法の矛盾にも切り込んでいかなければ常時介助が必要なお二人は議員バッジをつけた国会議員としての活動もできなくなります。
重度障害者だけではなく、
「生産性のない」というカテゴリーに属する人たちは今の社会では生きづらく、
山本太郎氏は「生産性で人間をはからせない世の中にしたい」という思いを選挙戦で掲げてきました。
自立支援と言いながら重度障害者が働きづらい環境にする現行法の矛盾はこれまでにも声を挙げてアピールしてきましたが、法改正というのは大きな壁で、2016年に障害者差別解消法が施行されても差別そのものはなくなりません。
その理由はいくつかあると思いますが、
「私たち抜きに私たちのことを決めないで(Nothing About us without us)」
というスローガンに耳を傾けることがないまま法律が作られ、
国会に障害のある当事者がいないことも大きいような気がします。
重度障害者が安心して暮らせる社会はすべての人にとって暮らしやすい社会になるだろうし、
今の社会から“バリア”がなくなって“フリー”となれば誰もが安心して生きられる社会になるはず。
そんな社会にしていくためにはまず国会から変えていく必要があります。
障害者が国会議員になった事例は過去にもあって、
少なからずバリアフリー化されてきた部分もありますが、
今回はスロープの設置とか本会議場の議席(スペース)の確保といった建物の物理的なバリアフリーだけでなく、
起立採決や記名投票といった障害故に不可能な表決方法の改善も必要で、
「仕事中はヘルパーを使えない」
という障害者総合支援法の矛盾にも切り込んでいかなければ常時介助が必要なお二人は議員バッジをつけた国会議員としての活動もできなくなります。
重度障害者だけではなく、
「生産性のない」というカテゴリーに属する人たちは今の社会では生きづらく、
山本太郎氏は「生産性で人間をはからせない世の中にしたい」という思いを選挙戦で掲げてきました。
自立支援と言いながら重度障害者が働きづらい環境にする現行法の矛盾はこれまでにも声を挙げてアピールしてきましたが、法改正というのは大きな壁で、2016年に障害者差別解消法が施行されても差別そのものはなくなりません。
その理由はいくつかあると思いますが、
「私たち抜きに私たちのことを決めないで(Nothing About us without us)」
というスローガンに耳を傾けることがないまま法律が作られ、
国会に障害のある当事者がいないことも大きいような気がします。
 でも、この日、新たな一歩が踏み出されました。
舩後靖彦氏と木村英子氏が取り組むのはシングルイシュー。
「障害があっても住み慣れた地域で安心して生きられる介護保障とバリアフリーなまちづくり」を実現するために当事者自ら国政の場でもっと議論して、
「多様性を認め合い、お互いを尊重する社会」
「誰もが生きていて良かったと感じられるような社会」にしていくこと。
そして、ものすごいスピードで国会議事堂のバリアフリー改修が始まりました。
重度障害のある当事者が国会に足を踏み入れるという、
今までには考えられなかった想定外の出来事に直面したからこそ、
「国会、動きます」となったのは間違いありません。
その先にはきっと障害の有無に関係なく、性別とか国籍とか門地とか肌の色とか関係なく、すべての人が安心して生きられる優しい国、日本をつくることにつながると思います。
「この国に生まれてきて良かった」ってね。
そういう意味でも障害当事者が国会議員として活躍できる環境のきっかけができたのは大きく、
これからさまざまな現場に「いい影響」が波及していくことに期待したくなるというもの。
でも、この日、新たな一歩が踏み出されました。
舩後靖彦氏と木村英子氏が取り組むのはシングルイシュー。
「障害があっても住み慣れた地域で安心して生きられる介護保障とバリアフリーなまちづくり」を実現するために当事者自ら国政の場でもっと議論して、
「多様性を認め合い、お互いを尊重する社会」
「誰もが生きていて良かったと感じられるような社会」にしていくこと。
そして、ものすごいスピードで国会議事堂のバリアフリー改修が始まりました。
重度障害のある当事者が国会に足を踏み入れるという、
今までには考えられなかった想定外の出来事に直面したからこそ、
「国会、動きます」となったのは間違いありません。
その先にはきっと障害の有無に関係なく、性別とか国籍とか門地とか肌の色とか関係なく、すべての人が安心して生きられる優しい国、日本をつくることにつながると思います。
「この国に生まれてきて良かった」ってね。
そういう意味でも障害当事者が国会議員として活躍できる環境のきっかけができたのは大きく、
これからさまざまな現場に「いい影響」が波及していくことに期待したくなるというもの。
海外の障害者国会議員
例えば、エクアドルの大統領レニン・モレノ氏 強盗に襲われて背中に被弾し、 下半身不随の車いすユーザーとなりましたが、 副大統領に就任後に真っ先に取り組んだのは「障害者支援」だったとか。コレア氏が大統領になるまで年約200万ドル(約2億円)だった障害者向けの予算は、1.5億ドル(約170億円)に増額。2008年には憲法を改正し、「障害者に対する差別や非人道的な扱いは犯罪」と明記するなど、障害者の権利を向上させました。また、各企業が少なくとも従業員の4%を障害者雇用に充てることを明記。約40万人分の車いすや約4000人分の義肢を政府が提供しました。 (withnewsより引用)
「日本だけではなく世界に対する私から言えるアドバイスは、障害者に対する差別を今すぐに根絶し、全ての人が真に団結するよう力の限り尽くさなければいけないことです。その結果は我々に希望をもたらし、より思いやりのある社会が生まれるでしょう。 障害者は今まで、社会から無視されていました。 今こそ彼らに光を当て、社会の中での次なるリーダーが生まれることが必要です」 (出典:エクアドルのモレノ大統領、書面インタビューより)例えば、バンクーバーの元市長サム・サリバン氏 19歳の頃にスキーの事故で頸髄損傷となった電動車椅子ユーザーですが、 すべての人が快適な毎日を送れるまちづくりを目指したアクセシビリティ先進国で、 障害者でもハイキングやヨットなどを楽しめるようにするための財団を設立。 どんな人でも快適な暮らしをするのはアクセシビリティとして当然。 なぜできないのか? 我慢しなければいけないのか? そんな些細な…それでいて当たり前の疑問だけど、 日本の多くの障害者は「仕方ないやん」という諦めの答えが真っ先に頭に浮かぶわけで、 でも、カナダ人の気質なのかどうかは分かりませんが、 「不可能なことはない」 「知恵と工夫があれば何でもできる」 という発想が先に出てくるのは国民性、あるいはカルチャーなのかもしれません。 いわゆる“弱者”のために特別な心配りをするのではなく、 どんな人でも等しくすることが結果的に豊かなアクセシビリティにつながるという考え方。
市区町村の地方議員
市区町村の議員はこれまでにもたくさんいましたが、 最近では「筆談ホステス」として話題となった斉藤里恵氏が良い事例。 今回、立憲民主党から比例代表で出馬するも落選しましたが、 斉藤元区議は2015年5月から2019年4月まで東京都北区議を務めました。 区議会では「音声同時翻訳ソフト」を全国で初めて導入し、 他の議員や職員のやり取りをタブレットで読んでやり取りしました。 情報保障の観点から言えば当たり前のことなんだけど、 当事者がそこにいて、初めて“気づき”が生まれることをアピールしてくれたように思います。障害当事者がやるべきこと
国政だけではなく、市政でも、府政でも、 あるいは政治の世界だけではなく障害者施策の決定機関(委員会等)にも、 当事者が参画することの重要性を実感させられる選挙で、 もっともっと障害者のことを知ってもらう必要があると痛感しました。 そのためには積極的なアピールも必要だし、 私たちには何が必要で、どんな支援を求めてるか? こちらからどんどん提示していかなければいけないですね。 変わることを待つのではなく、 変えるために自らアクションを起こしていく。 そんなことを改めて脳天から突きつけられた気分です。未分類 | 2019年8月1日